| リストラ天国 > コンテンツ > Diary |
−−−−−−−−−
日本の農業はどこへ向かうか マイカーで東京から京都まで旅行する場合 ゴルフをプレイしている人の年代層割合に驚いた 世界と日本の宗教別信者数 2021年版出版社不況 客員教授と非常勤講師ってなんだ? ロバート・B・パーカー「スペンサーシリーズ」全巻まとめ 窓ガラスの熱割れで火災保険は使えるか? 天然素材でも綿はよく燃えるらしいことがわかった やっとのことでJ:COMを退会した 貯まった1円玉はどうする? 自動車整備士に未来はあるか? 液晶テレビが壊れた件 リタイア後の心配事 運転免許証取得者は意外にも増えている 著者別読書感想INDEX −−−−−−−− 2002年 4月 2002年 5月 2002年 6月 2002年 7月 2002年 8月 −−−−−−−− 2020年 1月 2020年 2月 2020年 3月 2020年 3月 2020年 4月 2020年 5月 2020年 6月 2020年 7月 2020年 8月 −−−−−−−−
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ天国TOP おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX) 著者別読書感想INDEX リストラ天国 日記(BLOG) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リストラ日記アーカイブ 2011年6月 読みやすいようにアーカイブは昇順(上から古いもの順)に並べ替えました。上から下へお読みください。 日記INDEXページ(タイトルと書き出し部の一覧)はこちらです |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------- 5月の読書 2011/6/1(水) 502 「非国民」のすすめ (ちくま文庫) 斎藤貴男 著者は私と1歳違い(私のほうが1年上)ですが、本を読んでいると、考え方がしっかりとしていて、昔の頑固おやじタイプな印象を受け、後で年齢を知って驚きました。元々は新聞や雑誌、週刊誌の記者を務め、現在はフリージャーナリストとして活躍されている方です。 この本は2004年に出版されたもので、当時言論やプライバシーの危機だと叫ばれていた「コンビニや街角の監視カメラ設置」「自衛隊海外派遣と言論封鎖」「差別問題と階層」「住民基本台帳」「個人情報保護法」「MMR混合ワクチン問題」などを取り上げ、様々な証拠やインタビューから、政府、政治家、省庁、業界団体、マスコミに対して辛辣な批判を展開しています。 また決して自己満足の批判だけでなく、それぞれの問題に対し「支配されたがる人々」「無関心な人々」に対しても批判し、警鐘を鳴らしています。 著者はこの本以外にも数多くの書物を出していますが、2009年以降は新刊がなく、なにかあったのかなとちょっと心配なところです。私と一歳違いと言えば、まだ50歳代前半で物書きにとっては脂がのっている時期だと思います。 この本では、様々な雑誌や週刊誌などで書いた過去の記事やルポをまとめて1冊の本にしたような体裁です。そのため、強調をしたいからなのか、単に話しが重なってしまったのかわかりませんが、くり返し何度も同じ問題点指摘やフレーズが出てきます。 最初から1冊の本として書き下ろしたものであれば、もっとうまく組み立てられたのでしょうが、寄せ集めという感じはゆがめません。 一般の大手マスコミでは報道されない、深く突っ込んだ取材と、各種のデータを元にした論理展開は、同氏が専門紙や週刊誌記者を経験していたからできることでしょう。その批判の節々で出てくる、政治家、特にサラブレッドの二世議員に対する猛烈な個人批判については、著者が若いときに苦労した過去にその影響があるのかも知れません。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 国家の罠―外務省のラスプーチンと呼ばれて―(新潮文庫) 佐藤優 2005年に同氏が初めて書いた書籍です。その後お得意のソ連邦が崩壊した「自壊する帝国 (新潮文庫)」や自分を裏切った元職場を書いた「外務省ハレンチ物語 (徳間文庫)」など多数の本があります。最近紀伊國屋書店へ行くと、いずれの本も未だに目立つ場所に平積みされていたのには驚きました。ロングセラーなんですね。 ご存じの方も多いと思いますが、佐藤優氏は外務省勤務時代に、鈴木宗男衆議院議員とともに、対ロシア関係において出過ぎたまねをしたということで、小泉政権、外務省、マスコミから集中砲火を浴び、スケープゴート的にその表舞台から一度は消されてしまった人です。現状はと言えば、2009年に最高裁で上告を棄却され、背任と偽計業務妨害の罪で4年間の執行猶予期間中の身分です。 この本は、佐藤氏が今までになにをやってきて、その結果なぜ逮捕され、国策捜査の名の下に罪を着せられてきたかという、本人の自叙伝でもあり弁解録です。特に500余日も収監されていた東京拘置所での生活や、特捜部検事とのやりとりは、話半分としても読み応えがあります。 しかし本書の中には実名で「○○はこう言った」「○○は小心者で性格はこうだ」というようなことを平気で書いていますので、名誉毀損や、仕事の話しなどは守秘義務違反にならないのかとヒヤヒヤします。 確かにこの本に書かれた通りのいきさつがすべて真実であれば、佐藤氏が本当に罪として罰せられるほどのことかと思ってしまいますが、裁判での口述書など以外は、本人が書いた一方的な内容なので、いずれも話半分ぐらいにして読み進めていく必要があります。 その中には自分の仕事は国家にとって「すごく重要で、特別なんだ」という度を超した自負や思い込み、そして自分の行動を意識的に美化していると思われる箇所が多くみられ、相反する相手側から見ると、その行動や判断の善悪は180度逆転することになるでしょう。 ちょうど鬼籍に入る寸前の政治家や経済人が、日経朝刊の「私の履歴書」で、自分の過去の行動や決断を最大限に美化し、誇張して書くのと同質の匂いが感じられます。 以前読んだロシア語の通訳者で有名な、また多くの辛辣な書評を書いてきた米原万里の著書で、佐藤氏や佐藤氏の著作が何度も登場し、「素晴らしい人」「最高の出来」ということが書かれていたので、今回興味を持って読んだ次第です。米原氏とは同じロシアつながりで、しかも両氏とも国家機密に触れる同志的な親しい友人だった(米原氏は故人)のでしょう。 結構ボリュームのある本で、退屈だと嫌だなと思っていましたが、うまく過去の歴史や事件ごとにまとめられており、飽きさせない読み物となっています。ソ連邦の崩壊や、ロシアになってからの北方領土返還交渉、対ロシア外交の過程など、一般には知られることのない政治家の考え方がよくわかります。 その後も一向に解決しそうもない北方領土問題ですが、この本ではムネオハウス事件をきっかけにし、より一層難しくなってきたように読み取れます。 しかしそれは相手(ロシア)にしてみれば、鈴木宗男氏やインテリジェンスに優れた役人がどれだけ頑張ろうと、日本各地に大規模な米軍が駐留し、中国人民解放軍が急速に増強して力を付けてきている中で、そのロシア側の最前線緩衝地域となる北方領土を敵側にホイホイと返還するほど国際政治は甘くないでしょう。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ グロテスク (文春文庫) 上・下 桐野夏生 最近小説や映画で話題をさらった湊かなえ著の「告白 (双葉文庫)」を数年前に先取りしていた小説です。このような一人称で複数の登場人物が過去に起きた出来事をそれぞれの視点で語っていくスタイルはいくつもありますが、代表的なものとして芥川龍之介の「藪の中 (講談社文庫)」(映画のタイトルは羅生門)がもっとも有名でしょう。 ストーリーの中には、1997年に起きた「東京電力OL殺人事件」や「オーム事件」などが、登場人物のモチーフとして一部に使われており、39歳の慶応大学出身のエリート総合職女性が、渋谷のホテル街で日々売春を続け、不法滞在の若い外国人に殺害されるまでの経緯などが書かれています。 ただし、それはあくまで、サブ的なもので、本筋は、日本で生まれたスイス人ハーフの姉妹とその学友達の確執と転落がテーマです。 まず姉の告白から始まり、次に姉とは子供の頃から仲の悪かった妹の日記、さらには姉の同級生(殺害されたエリートOL)を殺害した不法就労外国人の調書、殺された同級生の日記へと続いていきます。 人間関係、特に女同士のドロドロとした関係が延々と続いていきますので、あまり体調のよくないときに読むと、精神的に落ち込んでいく可能性がありますので、やや注意かもしれません。なにか著者の比較的新しい作品「東京島」とも共通する、女性心理のいやらしいところをむき出しにした作品です。 ◇著者別読書感想(桐野夏生) ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 小説 サブプライム 世界を破滅させた人間たち (集英社文庫) 落合信彦 2009年に単行本が刊行された本ですが、最初はタイトルもよく見ずにお得意のノンフィクションかと思って読み始めたら完全に小説でした。 読み進めていくと服部真澄の小説だったっけ?と思うほど、アメリカ金融界に通じた内容の小説ですが、元々著者はその方面に強いということをすっかり忘れていました。最近はちょいイメージが違っていましたからね。 おそらく翻訳本やつまらないハウツー本も含むと150冊ぐらいの本を出しているであろう落合信彦氏の小説を読むのはホント久しぶりで、独特の雰囲気を持つ著者は好き嫌いが分かれるでしょうけれど、小説では彼の人脈や情報力でしか得られない裏話などが散りばめられていて私は嫌いじゃありません。 内容はタイトルにあるとおり、リーマンショックでアメリカの金融バブルが弾けてしまうまでを、LTCMの興亡、エンロン事件、9.11世界貿易センターテロ事件などウォール街の周辺で実際に起きた事件や、実在する機関や企業が複雑に絡み合いながら、その中で奮闘する優秀な日本人金融マンが主人公として描かれ、やがて破滅の2007年へと向かっていきます。 タイトルからすると金融専門用語が飛び交い、読むのに苦労するかな?と最初思いましたが、それは全くの杞憂で、大人の恋愛あり、FBIの無能ぶりあり、新宿の小さなバーの話しがありと、スラスラと軽く読めます。 -------------------------------------------------------------------- 再生可能エネルギーについて 2011/6/4(土) 503 原発事故が起きて、俄然自然エネルギーが注目されてきました。ただ自然エネルギーと言うと、広い意味では水力はもちろん、石炭や天然ガスなど天然資源を利用する火力も、そして元々は天然の鉱石であるウランなどを使う原子力も入ってしまうことになりますので、実際上「再生可能エネルギー」というのが適正かも知れません。 その「再生可能エネルギー」とは石油や天然ガス、ウランなどの「枯渇性エネルギー」の対義語として使われている用語です。 その再生可能エネルギーについてはマスメディアでもネットでも盛んに論議されていますので、今さらとは思いますが、自分の知識を整理しておくために書いておきたいと思います。日記ですからいいでしょう。 再生可能エネルギーは世界中で現在のところバイオ燃料、バイオマス、地熱発電、太陽エネルギー、水力発電、潮力発電、波力発電、海流発電、風力発電などがすでに実用化されています。 私は以前から日本列島の太平洋沿いに埋蔵されている「メタンハイドレート」が日本のエネルギー政策を救うものと言ってきましたが、これは天然ガスと同様「枯渇性エネルギー」で、しかも海底深くにあるためコストに見合った実用化ができるまで、まだ数十年はかかりそうです。 そしていま日本で原子力に変わる再生可能エネルギーとして注目されているのは、すでに古くから発電量で大きなシェアを占めている水力発電(揚水発電)や、今後期待値の高い太陽光発電、風力発電、地熱発電などがあります。 しかし環境破壊につながる脱ダムの政策からして、新たな巨大水力発電所の建設は難しく、代わりに日本の技術が生かせる太陽光発電や、欧州ではすでに一般的になっている風力発電に注目が集まっています。 まず太陽光発電ですが、アフリカ北部や中国西部、アメリカ、オーストラリアのように広大で利用価値がほとんどない砂漠地帯を持つ国では、滅多に雨が降らない砂漠に太陽光パネルを設置をすることで、天候に左右されることなく、年間を通して発電が可能となり、地域の昼間の電力をまかなっていくことが可能でしょう。 しかし天候が不順で、平均すると3日に1日は雨が降って太陽が出ない上に、国土が狭く平地も少ない日本では、極めて小規模な一般家庭や工場の屋根に設置して補完的に利用するしか役に立ちません。 最近は太陽光を電気に変える光電変換効率が技術の進歩で格段に上がってきていますので、将来に期待はできますが、それでも夜間は発電ができず、発電の主流とはなり得ません。 次に風力発電ですが、最近では海岸沿いや山間部に大きな風力発電用の風車をよく見掛けます。まだ外国製の装置が多いのですが、国産の製品も少しずつ増えてきています。 しかしこの風力発電も、年中適度な風が吹いている場所は限られていて、さらに人口密度が高い日本では、風車から出る高周波振動音が近隣住民に頭痛や耳鳴りといった健康被害をもたらしています。 また日本は台風が通過する位置にあり、そのような猛烈な風が吹く場合は危険なので風車は回らないように停止させますが、それでも過去の大型台風など自然災害により、故障したり、支柱部分がポッキリと折れてしまう事態が起きています。 地震が少なく、巨大台風の直撃もないヨーロッパで実績があっても、それをそのまま持ってきても日本では使えません。 最近では海上に設置したり、海上フロート型の風力発電装置の構想もありますが、実際の運用は陸上に設置するよりも難しく、それにやはり天候に左右され、補完的なものとしてはいいですが、年間を通して安定した電力を供給できるのかという点についてはやはり疑問が残ります。 そこで、いま一押しなのが地熱発電です。 日本列島には火山が走り、温泉が湧いていますが、その温泉の元である地熱(あるいはマグマの熱)を利用した発電方法です。しかもこの地熱発電装置(プラント)は富士電機が世界の約4割のシェアを持ち、続く三菱重工と東芝を含めると世界の7割のシェアがある日本以外で多くの実績がある発電方法です。 それだけの技術がありながら、日本ではほとんど地熱発電がおこなえずもっぱら海外へ輸出している状況です。 ただ地熱発電にもいくつかの超えなければならない問題があります。  まず、安定した地熱を取り出すためには、いくつも試掘をおこない常に高温の温泉が湧いている場所や、マグマに近い場所を探す必要があります。そしてその多くは国立公園内にあるので、現状では民間企業(電力会社等)が試掘調査の申請を出しても、自然公園法の規制で国(環境省)は環境破壊のリスクがあるためOKを出しません。 まず、安定した地熱を取り出すためには、いくつも試掘をおこない常に高温の温泉が湧いている場所や、マグマに近い場所を探す必要があります。そしてその多くは国立公園内にあるので、現状では民間企業(電力会社等)が試掘調査の申請を出しても、自然公園法の規制で国(環境省)は環境破壊のリスクがあるためOKを出しません。もし最適な候補地があったとしても、国民共有財産の国立公園内に民間のプラントを建設するなんてもってのほかと拒否されてしまいます。 電力供給会社は経産省、国立公園管理は環境省、温泉利用は厚労省と言ったところで、縦割り行政の弊害でもあり、また同時に環境保護活動の高まりにより、国策で風光明媚な海岸に原発を作ることは出来ても、国立公園内にほぼ無公害な地熱発電プラントを作ることができないのです。 次に、温泉が湧く場所で国の管理地以外では、通常既に温泉街やその温泉を元にした観光地が作られています。そのすぐそばで大規模な掘削や発電所(タービン建屋)を作ることは、その温泉地が享受している源泉の湯量や周辺の環境に影響を与えてしまうことが懸念されています。 そのような既得権益を持つ温泉旅館組合や企業、市町村などの建設反対派に対し、民間会社が個々に交渉し、補償金を支払っていくというのも現実的には難しいでしょう。 以上のことから、大規模な地熱発電を作るには、設置場所さえあればすぐに始められる太陽光や風力と違い、原子力発電所の建設と同様、国策として多少無理を覚悟して押して進めていくしかありません。 地熱発電は、有限資源であるウランを使ったり、使用済みの核燃料を廃棄するため何百年と地中深く保管し、負の遺産を後世に残すこともなく、また今後高騰や激しい争奪が予想される石炭、石油、天然ガスの確保や、やっと確保してもはるか遠くの国から輸送してくる必要もなく、さらに化石燃料を燃やして出る二酸化炭素の問題もなく、太陽光や風力発電のように天候に左右されることもない、日本の国土の特徴を生かした21世紀の最良の発電方法ではないかと思うわけです。  また一度地熱発電所を建設すれば、原発や火力発電のような危機管理、安全管理の必要性はなく、保守や運用、セキュリティのコストはほとんどかからず、日常は無人運転さえ可能と言われています。 また一度地熱発電所を建設すれば、原発や火力発電のような危機管理、安全管理の必要性はなく、保守や運用、セキュリティのコストはほとんどかからず、日常は無人運転さえ可能と言われています。海外のエネルギー問題を研究している学者からは「日本は地熱資源の宝庫で羨ましい」とまで言われているぐらいで、その地熱資源の保有量は、米国、インドネシアに次ぎ世界で第3位と言われています。 あとは発電するコスト計算で、地熱発電はいつも他の発電方法より飛び抜けて高く見積もられてしまいますが、燃料代や輸送コストの高騰、環境問題、事故が起きた際の賠償リスク、保守・運用コスト、安定性などを総合的に考えると、いずれは、いや既にそのコストは逆転しているのではと考えられます。 設置する場所は、環境保護団体や地元観光業界から猛烈な抗議や批判がくることを覚悟して、法律を変え、全国の火山を持つ国立公園内に発電所を設置することを義務づければ、新たな土地取得費用は発生せず、また民間の既存温泉地からはできるだけ離れた場所に設置することが可能となります。 発電所からは水蒸気や熱湯は出ますが、二酸化炭素や放射能を出すわけではありませんので、自然環境にとっても優しいのです。 また温泉がわき出る場所というのは、一般的には農林業か観光業しか就職先がない奥深い山奥に多いのですが、そこに発電所や送電所、変電所、または大量の温泉水を利用したレジャー施設や工場を作ることも可能です。そうなると新たな雇用先が生まれ、原発ほどではないですが産業新興にもつながります。 騙されてはいけないのは、地熱発電反対派からは、地熱発電所によって自然が無惨に破壊された外国の写真や映像が、意図的に加工して出され、また因果関係はなくとも、近くの温泉が枯れたとか、火山が活発化して被害が出たといった悪意ある情報が出されます。また利用した熱湯は再び地下に戻されますので、資源が枯渇すると言うことはありません。 なにごとをするにも、すべての人に歓迎され喜んで受け入れられる事ばかりではないと理解していますが、例えいくつもの障害があろうとも、日本の未来を考えると今もっとも力を入れて進めなければいけないのが地熱発電ではないかと思っているわけです。 最後に次世代のエネルギーと言われているメタンハイドレートについて簡単に。 深海深くに存在するメタンガスが氷状に凝縮した結晶がシベリヤの永久凍土の中や日本列島の近海に大量に存在することがわかっています。これは高任和夫著の小説「燃える氷 」に素人にもわかりやすく紹介されていますが、もしこれがコストに見合うように実用化されると、日本は一躍世界有数のエネルギー資源大国となります。 ただし、海底深く(数百メートルから数千メートル)に冷えた状態の固体として存在するため、石油や気体のように吸い上げることはできず、また引き上げる際に温度の上昇により、気化してしまう難しさがあって、現在のところコストをかけずに取り出す方法が見つかっていません。 しかしいずれ技術の進歩や画期的な方法が見つかれば、少なくとも数十年のあいだは、石油や天然ガスの輸入は最小限で済むようになり、日本中、電気自動車と並んでメタンガスエンジン車が一般化するようになるかも知れません。 【参考サイト】 地熱発電、日本企業が世界シェアの7割 課題は環境規制との両立 レスター・ブラウン氏に学ぶ「地球温暖化防止」 日本はもっと地熱発電を 米国の環境学者 レスター・ブラウン氏提言 資源量は世界3位、火山国ニッポン「地熱発電」に活路! 元GE技術者・菊地洋一さん講演 -------------------------------------------------------------------- エアコンの購入 2011/6/8(水) 504 今から19年前(1992年)、子供達が大きくなってきて、それまで住んでいたマンションが手狭になってきたので、思い切って「いかにも安普請の一戸建て」を購入しました。新築9棟現場のうち、完成後半年経っても半分が売れ残ったまま空き家状態だったので、思いっきり値引きしてくれたものです。 でも一戸建てと書くと一般的にはリッチな感じもしますが、その時はすでにバブルは弾けた後で、場所を気にしなければ、狭い建て売りの一戸建てと、新築マンションとを比べると、その値段の差はほとんどありませんでした。 建て売り一戸建ては、2階建ての4LDKタイプなのですが、当時としては珍しく最初から各部屋にエアコンが設置されていて(今では普通かもしれません)、LDKの1台を含め合計5台(当時のエアコン価格推定で約100万円程度)分のお得感がありました。 しかも装着されていたのは、割と高級機として有名だった三菱重工のビーバーエアコンで、マルチ型室外機が2台(室内機合計4台)と広い部屋用の機種1台(室外機室内機とも1台)です。
INAX 洗面化粧台 (洗面台) NEW PTシリーズ 間口600mm セットQ 一般地仕様 化粧台本体:PTXN-605S(S) ミラーキャビネット:MPTX-601Y 同種のD7シリーズ品番(D7N1-605S)(D7-601YU) ○くもり止めヒーター:なし ○水栓金具:シングルレバー洗髪シャワー水栓 ○写真洗面器カラー:ピンク ○セット寸法:600×520×1780(mm) ○写真扉カラー:ホワイト ○写真洗面器カラー:ピュアホワイト ○化粧台本体:PTXN-605S(S) ○ミラーキャビネット:1面鏡(白熱灯照明) MPTX-601Y さて、次回は、怒濤?の工事編です。 LIXIL 洗面台 幅600mm両開き ホワイト ミラー LED照明 PV1N-605S(4)Y/VP1H + MPV1-601YJ INAX -------------------------------------------------------------------- 洗面化粧台をDIYで交換 その2工事編 2011/6/21(火) 508 前回の「その1準備編」に続いていよいよ洗面台の設置工事です。このブログ用にすべての工程で写真を撮っておこうと思ったのですが、家の全部の水栓を止めていたこともあり、気が急いて余裕がなかったのでまったく撮ってません。 土曜日の昼過ぎに洗面台とミラー部が大きな二つの段ボール箱に入れて送られてきました。洗面台には、まだ蛇口の部分や水栓レバーは本体に取り付けられていないので、それを先に組み立てておきます。 スパナやレンチの入らない狭い場所で締め付ける必要があり、買っておいた立水レンチが役に立ちました。 さて交換作業の順序としては、 1)屋外にある止水栓を締める 2)壁の止水栓と古い洗面台水栓、排水用の管を切り離す 3)洗面台とミラーを取り外す 4)壁や床の清掃、補修 5)洗面台裏面に止水栓を通すための穴空け 6)洗面台の床下に排水口用の穴空け 7)壁から突き出てる止水栓(水と温水)を新しいものと交換 8)洗面台の設置 9)止水栓と洗面台水栓の接続 10)排水パイプの接続 11)ミラー部を壁に取り付け 12)屋外水栓の開放(反時計回り) ってところです。 要注意箇所は7)の止水栓の交換と9)10)の配管接続でしょう。いずれもシールテープをたっぷりと巻き、ねじ込みが緩いと水漏れを起こし、逆にレンチなどで強く締めすぎるとネジ山をつぶしてしまう可能性があります。 5)6)の洗面台の配管用穴あけはそれほどナーバスにならなくても、普段は見えない場所ですから、多少大きめに穴を空けても問題なしです。先の尖った小振りのノコギリがあると便利です。薄いベニヤ板ですからカッターでも時間はかければ切れます。 意外と時間を取るのは、4)壁や床の清掃、補修で、もし床面が腐っていたりカビだらけだったり、壁面の壁紙が濡れてはがれそうになっていたりすると、その清掃と補修は結構大変です。しかも古い洗面台を除いてみないとその状況がわかりませんから、ぶっつけ本番です。 マンションなど鉄筋コンクリートの床なら問題ありませんが、木造の場合、万一床部分が腐っていたら、補強のために板を敷くとか、腐った板を新しい板と交換するなど大きな補修が必要になってきます。床面の全面交換となると素人の手に負えなくなってきます。 以下、作業と注意点です。 1)屋外にある止水栓を締める 2)壁の止水栓と古い洗面台水栓、配水管を切り離す →切り離すとき配管の中に残っている水が飛び出すので注意です →止水栓やフレキシブルホースを再利用する場合は丁寧に取り外しが必要です(最低限パッキンは新品に交換) →私は止水栓は新品に交換、ホースは新しい洗面台に付属していたもので足りました 3)古い洗面台とミラーを取り外す →数カ所ネジ止めされているだけです。しかしこれが固く固着していてたいへんでした →洗面台の下からゴキちゃんの死骸1匹が出てきました(;´Д`) 4)壁や床の清掃、補修 →洗面台周辺の壁紙がひどく汚れていましたが壁・床面にカビや腐食はなく、ビニールの壁紙を上張りしました 5)洗面台裏面から止水栓を通すための穴空け →大まかにメジャーで測って、だいたいの位置に穴を開けましたが、ピッタリとはいかず再度穴を拡大する必要がありました。ちょっと不格好に。このあたりやり慣れているプロなら綺麗に処理できるのでしょう。 6)洗面台の床下(底)に排水口用の穴空け →新しい洗面台に最初から空いていた穴の位置と床の排水管の位置が10cmぐらいずれていて、横に拡大して開ける羽目に。洗面台の幅とか奥行きとかは例えメーカーが違っても決まっているのだから、こういう位置も規格を決めておいてもらいたいものです。最初から開いていた大きな穴はとりあえずガムテープで塞ぎましたが長持ちしないので別途ベニヤ板で補修予定 7)壁から突き出てる止水栓(水と温水)を新しいものと交換 →洗面台設置後に止水栓のシールテープを巻くのは狭くてたいへんなので洗面台設置前に巻いておくのが便利です →先に止水栓も取り付けてしまうと5)の穴も大きめに開けることになります 8)洗面台の設置 9)止水栓と洗面台水栓の接続 →水栓に標準で付いてくるホースが意外と長く、事前に買った延長ホースは2本とも必要ありませんでした →そしてもし必要だったとしてもその準備したホースでは役に立ちませんでした →使用できない理由はホースの両端のネジ形状が買ったのが「メス=メス」×で、必要なのは「メス=オス」○でした 10)排水パイプの接続 →特に問題なく押し込むだけ 11)ミラー部を壁に取り付け →通常洗面台と隙間を空けずに上に乗せるように設置しますが、背の高い長男の要望により約10センチ上にあげて設置しました →そのことにより洗面台とミラー部との間に飛び散った水が入ると洗面台の下が水浸しになります →洗面台と壁面の間にポリシートを両面テープで挟み壁と隙間ができないようにしました  12)屋外水栓の開放 →その後洗面台下の止水栓を少しずつ開けて開通です →水漏れしないか、排水がちゃんと流れるかしばらく水やお湯を出してチェックします 以上で完成です!かかった時間は高校生の息子と二人でゆっくりやって2時間ぐらいです。そのうち壁紙貼りに30分程度かかりました。  シングルレバー&引き出し可能シャワー水栓付きで、洗面ボウルの高さもちょうどよくなりいたって満足です。 -------------------------------------------------------------------- 本屋大賞ノミネート作品 2011/6/25(土) 509 本屋大賞というのがあって、毎年書店員さんの投票で作品が表彰されています。私は読者の感性や消費者マインドをよく知っている書店員さんの書評を、他の週刊誌・新聞の書評やプロが選ぶ文学賞よりもずっと信用していますので、この本屋大賞は購入する本の参考になります。 しかし残念ながらこの大賞に選ばれるのは、その年に刊行された主として単行本ですから、発表後すぐに買うことは財政上無理なので、人から借りられる場合を除き、文庫化されるまで待つことになります。中には1年以上経っても文庫化されないものもあり、悲しいけれどそういう本は物覚えも悪くなってきたこともありサラッと忘れてしまうことにしています。なので、購入する本は1年以上前の受賞作が中心ということになります。 ちなみに2007年から2011年までのベスト10はこんな感じです。
本屋大賞は第二次投票以後のベスト10しか一般向けには公表されていませんが、実はここには上がっていない11位以下の、一部の書店員さんが熱く推奨する本があります。 私的にはその本こそ知りたいなと思うのですが、残念ながらネット上ではオープンにされず、「本の雑誌 増刊 本屋大賞」を書店で買ってくれという流れになっています。このご時世にまったくせこいことです。 所詮書籍を売るための宣伝が目的である雑誌を高い金を出してまでわざわざ買うことはありません。無料で読める書評なんて世の中に星の数ほどあるわけで、本のPR誌ごときにお金を出すぐらいなら、一冊でも多く著者の収入につながる本を買います。 ここ何十年と、年間100冊ぐらいは読んでいますが、それにしても本屋大賞ベスト10に入った本は自分でも意外ですがあまり読んでいないことに気がつきました。2010年以前のものはすでに文庫化されている本が多く、多くは書店で平積みされていて、タイトルを見れば表紙のデザインまで思い浮かんできます。 しかしなぜ買わないかというと、書店では実際には手にとって文庫のカバー裏にある簡単な紹介文を必ず読んで買うか買わないかを決めるので、そこではねられたものが多いと思われます。 それゆえに文庫の裏表紙の紹介やあらすじは、いかに読みたくなるように編集者の腕の見せ所でもありますが、実はあまり重要視されていないような気もします。もしかすると書評や各賞よりも、売れ行きに影響するさらに重要なポイントなのかも知れないのですが、そのようなことは現場の人はあまり知らないのでしょうけどね。 逆に目立つようにど派手な色遣いの帯や、その帯に書かれた「○○氏推奨」の大きな文字はかえってイメージが悪い(下品な感じ)のですが、必ずある一定の割合で存在します。 逆に多くの文庫本の本文の最後に書かれている解説は、私に限って言えば、本文より先に読んだことが一度もないので、そこに「書店でこの解説を読んでいる人は間違いなく面白いのですぐに買いなさい」とか「これ以上書くとネタバレするから」とかあるのはまったく意味のないことです。 長年書店で文庫本を物色するのを趣味としてますが、解説をじっくり読んでいる人を見掛けたことがないのですが、そのような人が実際にいるのかどうかは不明です。 しかしわざわざこのような常套句を解説に書くのはやめてもらいたいものです。少なくとも解説に面白くない本に「この本は駄作なので買わない方がいい」と本音が書かれることはないので、それをもって買うか買わないかの参考にはなりません。 -------------------------------------------------------------------- 生活保護受給者200万人時代 2011/6/29(水) 510 「今年3月末現在の全国の生活保護受給者は202万2333人(世帯数145万8583世帯)で、戦後混乱期の1952年度以来、59年ぶりに200万人を突破したことが14日、厚生労働省の発表で分かった。また受給世帯数も1952年度の統計開始後、過去最多を更新した。」という記事がありました。 日本の人口は1億2800万人ですから、その中で生活保護を受けている人の割合は1.6%で、世帯数で見ると全体で約3%、高齢者世帯を抜粋すると6%超となります。世帯数で見ると割合が高くなるのは単身世帯の受給者が多いことを指します。 そして生活保護予備軍として、この先65歳になっても年金がもらえない65歳以下の人は全国におよそ80万人いて、さらにこのままだと年金はもらえないが、過去にさかのぼり高額の年金を一度に支払うことができれば些少な年金が支給される人が約110万人います。 ここからは推測ですが、過去にさかのぼって掛け金を一括して支払えば年金がもらえる110万人の中高年者のことを考えてみると、単純に忘れてたという人は少なく、経済的な理由や信条から支払ってこなかった人が多く、例えば過去10年分妻と二人分360万円を一度に支払えるかというと、あまり現実的ではないような気がします。そのような中高年者は結局年金ではなく生活保護を選ぶことになるでしょう。 この合わせて190万人の無年金予備軍はすでに中高年層で(若年層はこれから支払えば25年に足る)、経済環境から50歳代以上の再就職は難しい上に、肉体的にもどんな労働もいとわない人ばかりとは限りません。 逆にこの無年金予備軍の中には、年金や生活保護に頼らなくても、すでに老後の資金を十分に蓄えている人や、老後は子供や親族に扶養してもらえる人達がいると思われますので、全員が無年金で生活保護に頼るというわけではありません。 しかし核家族化、少子化、DINKS(子供なしの共稼ぎ夫婦)の世代が高齢化を迎え、頼るべき子供や親戚がいないケースや、長引く不況とデフレで、社会人になった子供は正社員ではなく、収入や雇用に不安定なフリーターだったりするケースもありますので、とても親の面倒まで見られないという現実的な問題も考慮しなければなりません。ニートで無収入な子供が親の年金を頼りにして暮らしているというニュースも最近よく耳にします。 またある程度の貯蓄や財産を持っている人は、今まで年金を支払ってこなかったとは考えにくいので、年金受給資格に満たない人の多くは、手続き上のミスでなければ、裕福な世帯ではないことが容易に想像ができます。 それらを考えると、現在200万人の生活保護者数に、今後10数年のあいだに上記の無年金予備軍190万人のうちザックリ半分の100万人が、新たにな生活保護受給者として加わってくる可能性があります。さらに世帯主の完全失業者が150万人を突破しようとしている中で、このまま若年層、中高年層の雇用状勢が改善しなければ、無年金高齢者との相乗効果(今までは無職の子供でも親の扶養や援助でなんとか暮らせていた)によって劇的に申請が増えていくことになります。 日本の場合、本来は生活保護が受けられる立場であっても、世間体を気にしたり、あるいは知らなかったということで受給していない潜在的な生活保護者候補が相当数いると言われています。役所へ申請に行ってもなんだかんだと高圧的に門前払いされるケースもあると聞きます。 また役人に著しくプライドを傷つけられ、頭にきて申請を取り消すようなこともあるそうです。役所からすれば、受給率(人口に対する生活保護者数の割合)がそれぞれの役所で低いほど評価される仕組みですから、なんとか支払わなくても済むよう努力をします。 また誰からも扶養されていない年金だけで生活している高齢者の年金支給額が、生活保護の受給額と比べて少なければ、その差額は生活保護の申請をすればもらえます。しかし福祉費の支出をできるだけ抑えたい役所が、それらを積極的にPRすることはありません。 すでに財政的には年金はパンクしていると言われていますが、人口統計を見れば年金システムが将来どうなるのかというのはあきらかで、これほど予測しやすいものはありません。それを知っていながら、なにも手を打ず、政治家や役人への利益誘導をしてきた歴代の与党政治家(自民党)と、厚労省官僚達の責任はとても重いはずです。 しかしそのツケは誰も責任を取らず、挙げ句の果ては消費税アップをおこない「無年金者に対しても平等に年金を」とか言い出しています。 税金を上げて、年金を納めてこなかった人にも年金を支払うというのは、真面目に25年以上年金掛け金支払ってきた人にとって不平等であることは一目瞭然です。かといって、無年金者の多くが将来生活保護を申請するなら、結局は税金を投入することとなり同じことです。 少なくともこれらを改善するには、責任ある政治家と官僚に最大の痛みを持ってもらうため、議員数と厚生労働省役人の大幅な削減と、家賃の高い霞ヶ関から出て僻地への移転、議員住宅や公務員住宅などの特権や優遇策の撤廃を最低限の条件として実行してもらい、その後ならば仕方がないかなと思っています。でもきっと既得権益は絶対に手放したくないのでできないでしょう。 また生活保護は本来憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ために、母子(父子)家庭への育児中の経済・教育支援や、身障者や病気・怪我で働けない人への生活・福祉支援であったはずですが、いつの間にか、職をなくした自由労働者と、「ヤ」がつく自由業の人達、無年金高齢者の多い制度になってしまい、それが過去最大となり、今後も増え続けていくというのが生活保護の実態なのでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----------------------------------------------------------
年別 日記INDEXページ(タイトルと書き出し部の一覧)
リストラ天国TOP おやじの主張(リストラ天国 日記INDEX) 著者別読書感想INDEX リストラ天国 日記(BLOG) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

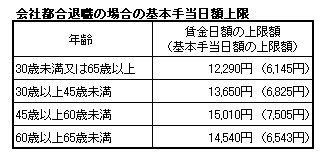
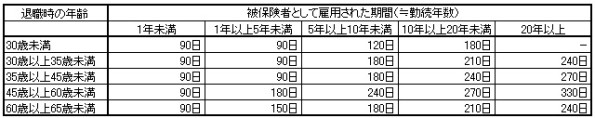
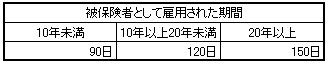
 壊れたのは建て売り住宅に最初から付いていた安物のマイセット(MYSET)の水栓と温水栓が別々の2栓タイプの洗面台で、分離しているミラー部はかなり汚れているものの使用に問題ありません。
壊れたのは建て売り住宅に最初から付いていた安物のマイセット(MYSET)の水栓と温水栓が別々の2栓タイプの洗面台で、分離しているミラー部はかなり汚れているものの使用に問題ありません。
